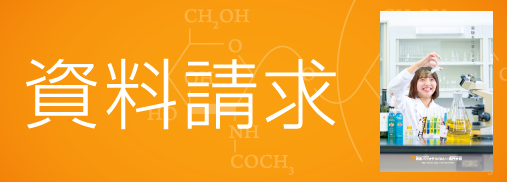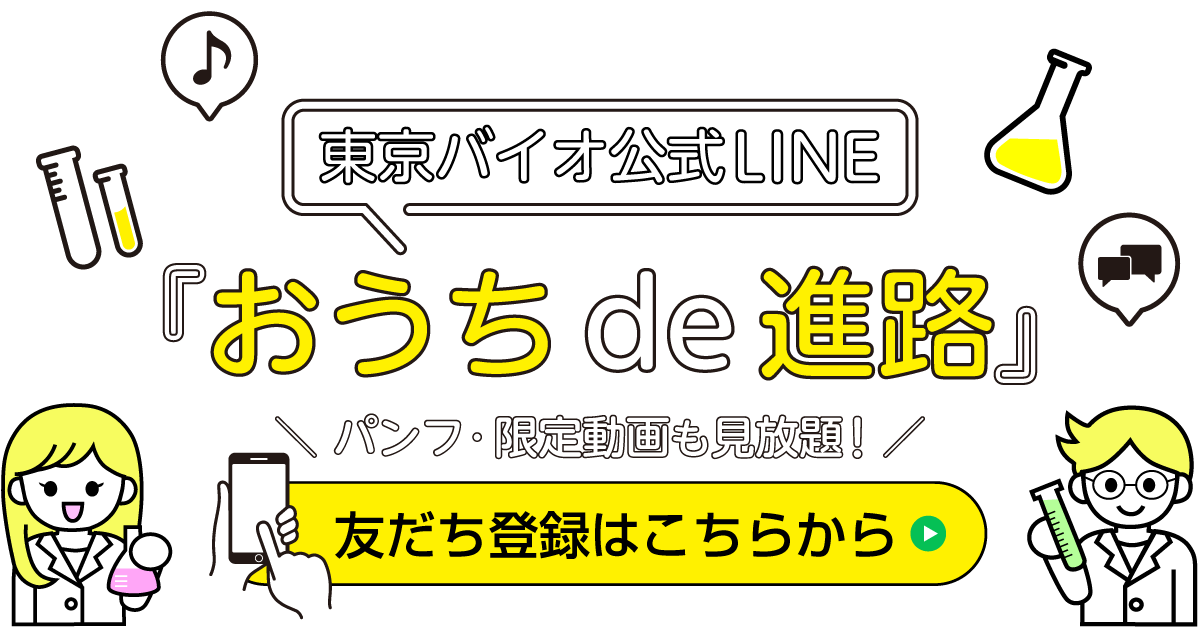【ビールの造り方】発酵~自然発酵~
投稿日:
ビール醸造の発酵には
・上面発酵
・下面発酵
・自然発酵
の3つがあります。
今回はこのうち「自然発酵」について、
解説していきたいと思います。
自然発酵のビールといえば、ベルギーのランンビックが挙げられます。
ランビック(Lambic)は、培養酵母を使用せず自然発酵によって醸造する古典ビールです。

20年ほど前に東京バイオに醸造発酵コース(ワインの醸造免許(試験)を取得して、ワイン醸造が学べるコース)ができた最初の海外研修先は、なぜかワインではなくベルギーでビールを知る研修となりました。
ビール醸造については、ほとんど知らないまま、学生と見学したのは大手ビール会社、小規模なビール醸造所など、ベルギービールの種類の多さに驚きながら見学をさせていただいたなかに「ランビック」ビールの醸造所がありました。
ランビックについて知識がないまま見学したところで印象に残っているのは、2月の2週間ほど間、麦汁が醸造所の屋根裏にある底の浅い冷却層で一晩冷やされ、寒い冬の星降る夜にその麦汁に空気中の微生物が舞い降りてビールを造るのだということ、そして、この地域のみの特徴的な醸造であるという部分でした。
空中落下菌といえば空中落下菌であるが、その土地のその時期の環境が作り出す、寒さ・湿度・風向きなどがビールを造る微生物を連れてくるというロマンティックなストーリーのビールが貴く感じられます。
ビールの造りや味わいなど特徴を知って、研修に出ていればもっと有意義な体験ができ、多くを学べた機会になったであろうと後悔の多い思い出となっています。
ランビックは、大麦麦芽(約60%)、小麦麦芽(約40%)、1年経過した古いホップを多量に(6~9㎏/kL)使用し、約2年をかけて自然発酵を行います。
ランビック特有の香味成分の形成に最初に出てくるのは、通常のビールでは汚染細菌であるEnterobacteriaceae科の細菌類です。
この細菌の生成物と他の微生物の生成物が混合した状態になるとランビックに特徴的な香味を形成します。
次にSaccharomyces属の酵母が出て、アルコール生成に働きます。そして、Pediococcus属などの乳酸菌が乳酸を生成し、特有の酸味が醸成され、酢酸菌によって酢酸が生成される場合などもあります。後発酵酵母のBrettanomyces lambicやB. bruxellensisなどにより酢酸エチル、乳酸エチルなどのエステルが合成され、ランビックに特徴的な高含量のエステルとなります。
ランビックの他の自然発酵ビールの多くは、酵母によるアルコール発酵と乳酸菌による乳酸発酵を主体とするものが多くなっています。
微生物が次々出ては消える繰返しで醸造される「ランビック」ぜひ皆さんも味わってみてください。
参考文献等
・多和田 悦嗣:第25回EBC「欧州ビール大会」、日本醸造協会誌, 90, 845, 1995
・村上 満:修道院とビール “Abbey And Beer”, 日本醸造協会誌, 79 , 869, 1984
・横山 直行:ベルギービールについて, 日本醸造協会誌, 94, 804, 1999
・高橋 礼介:ビール醸造微生物学の進歩(3), 日本醸造協会誌, 81, 315, 1986
社会人向け醸造家に学ぶ講座
実験ができる体験実習開催中
東京バイオでは、毎週末実験ができる体験実習を行っています。
また、週末忙しいい方のために平日説明会も開催中。
是非お越しください!